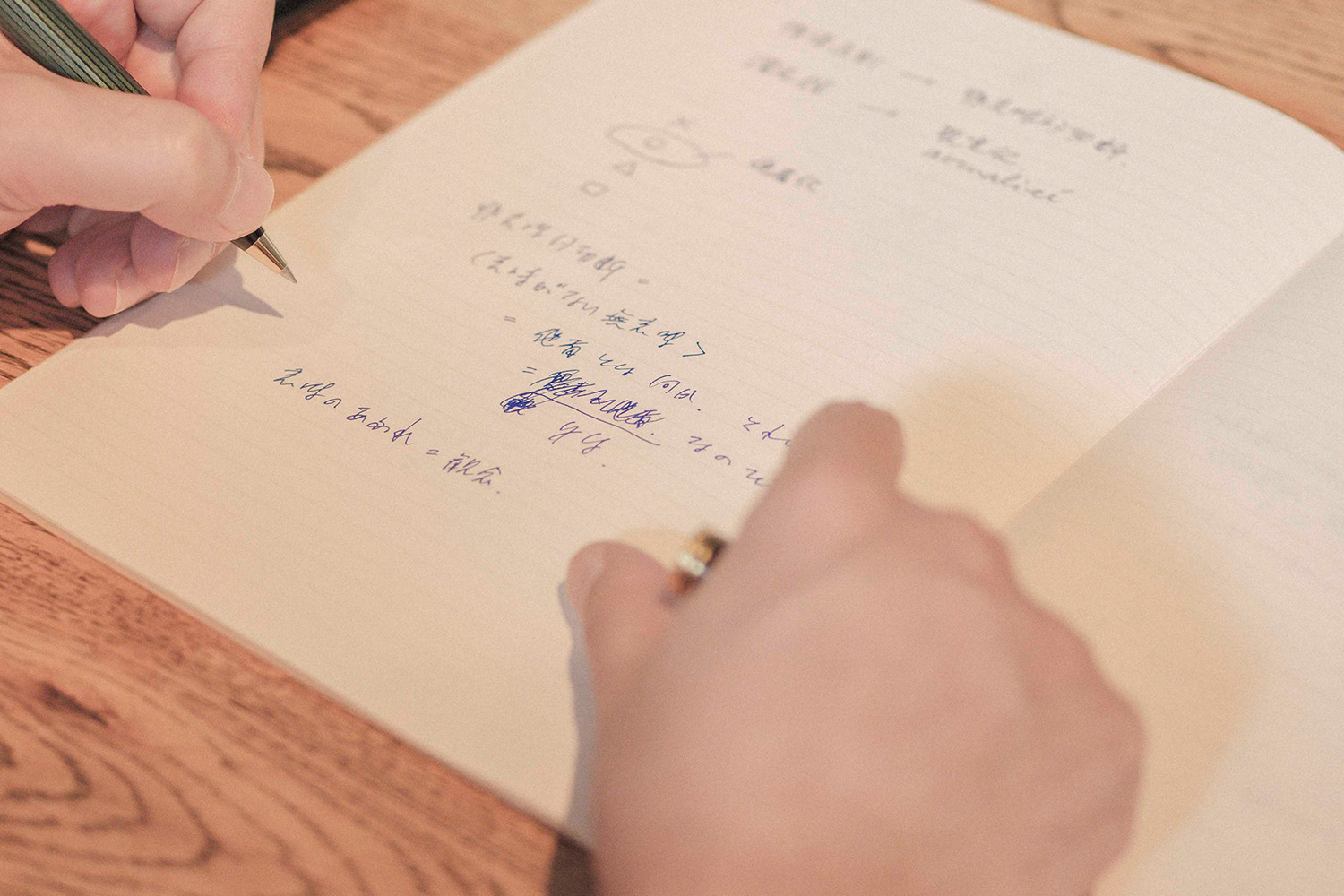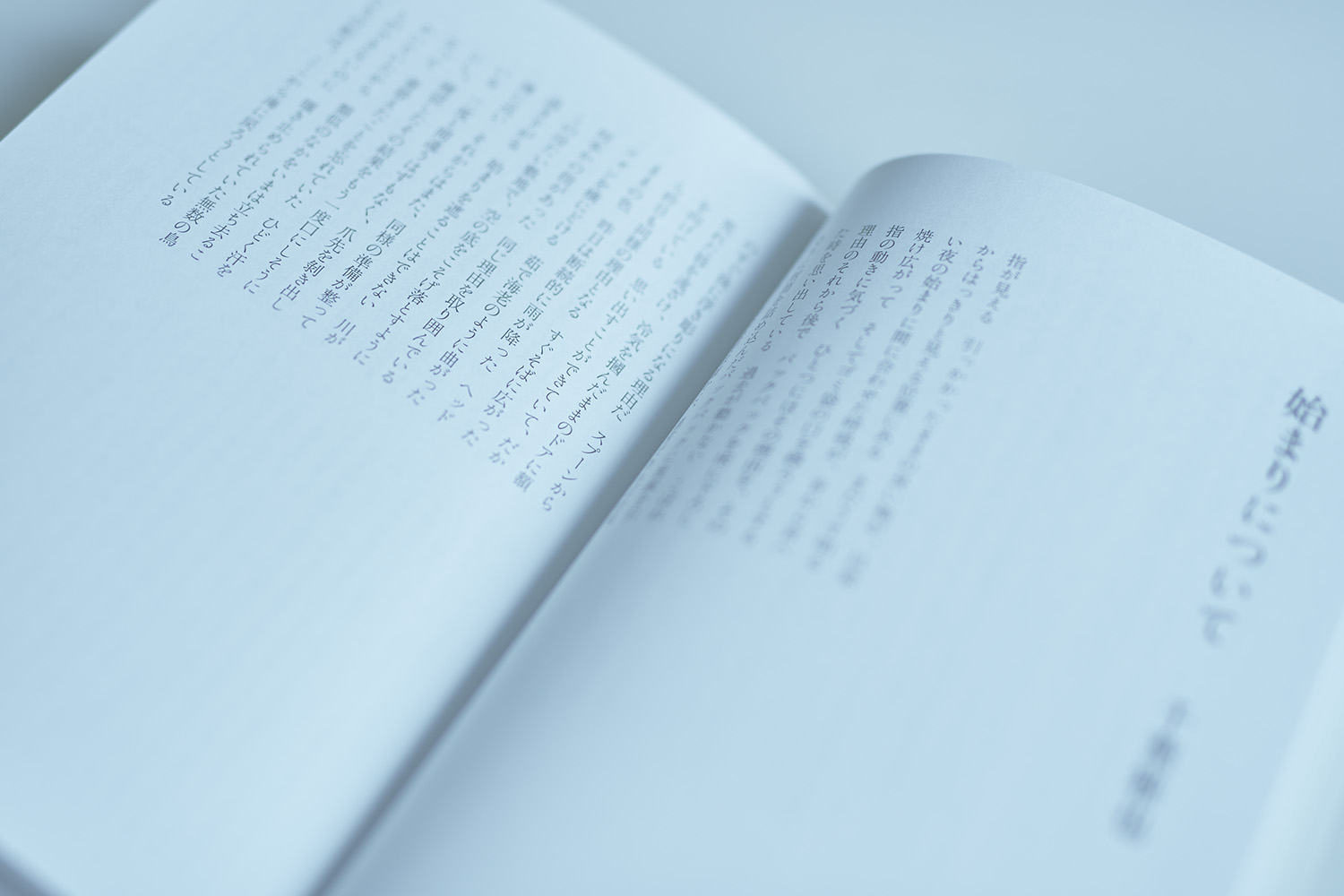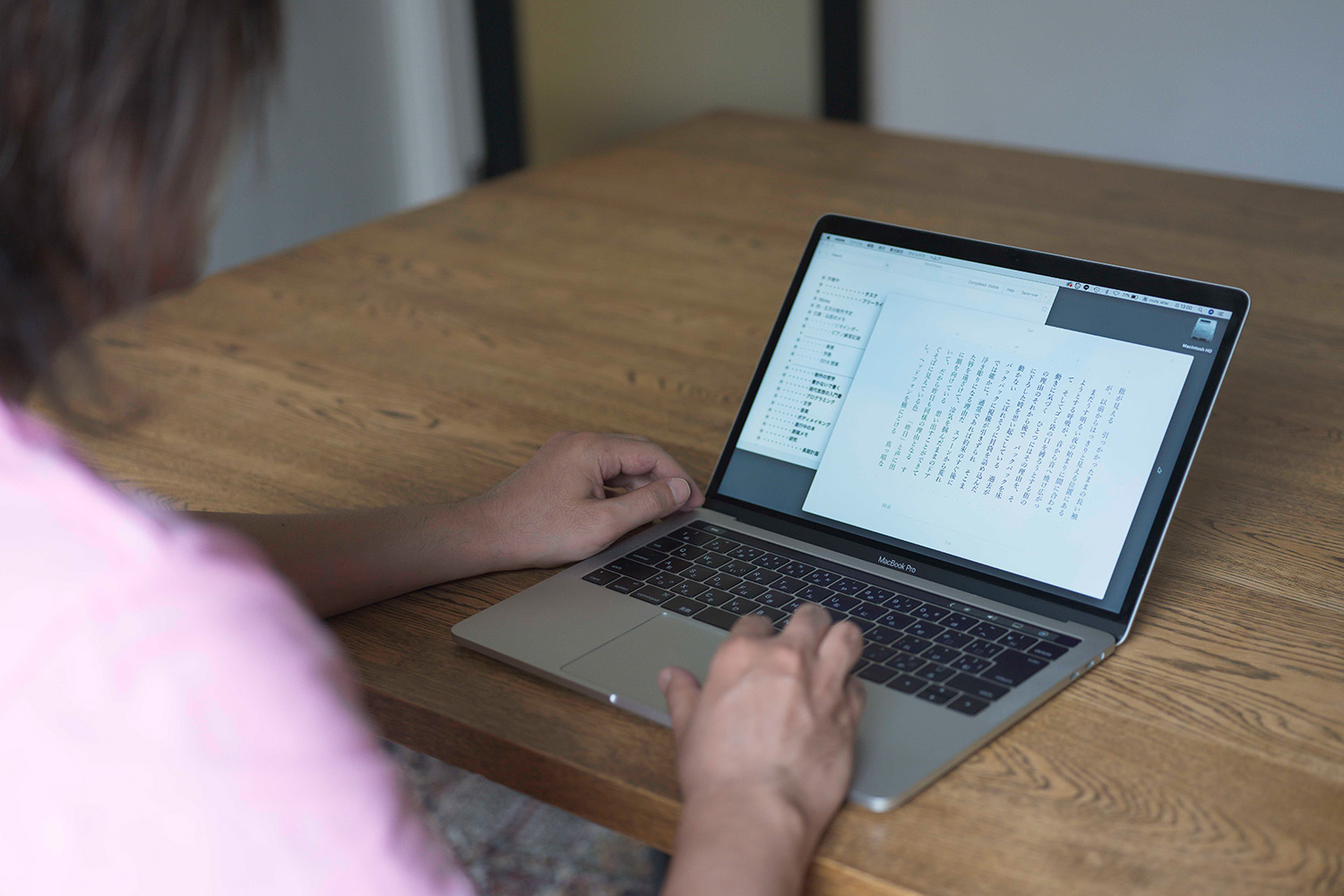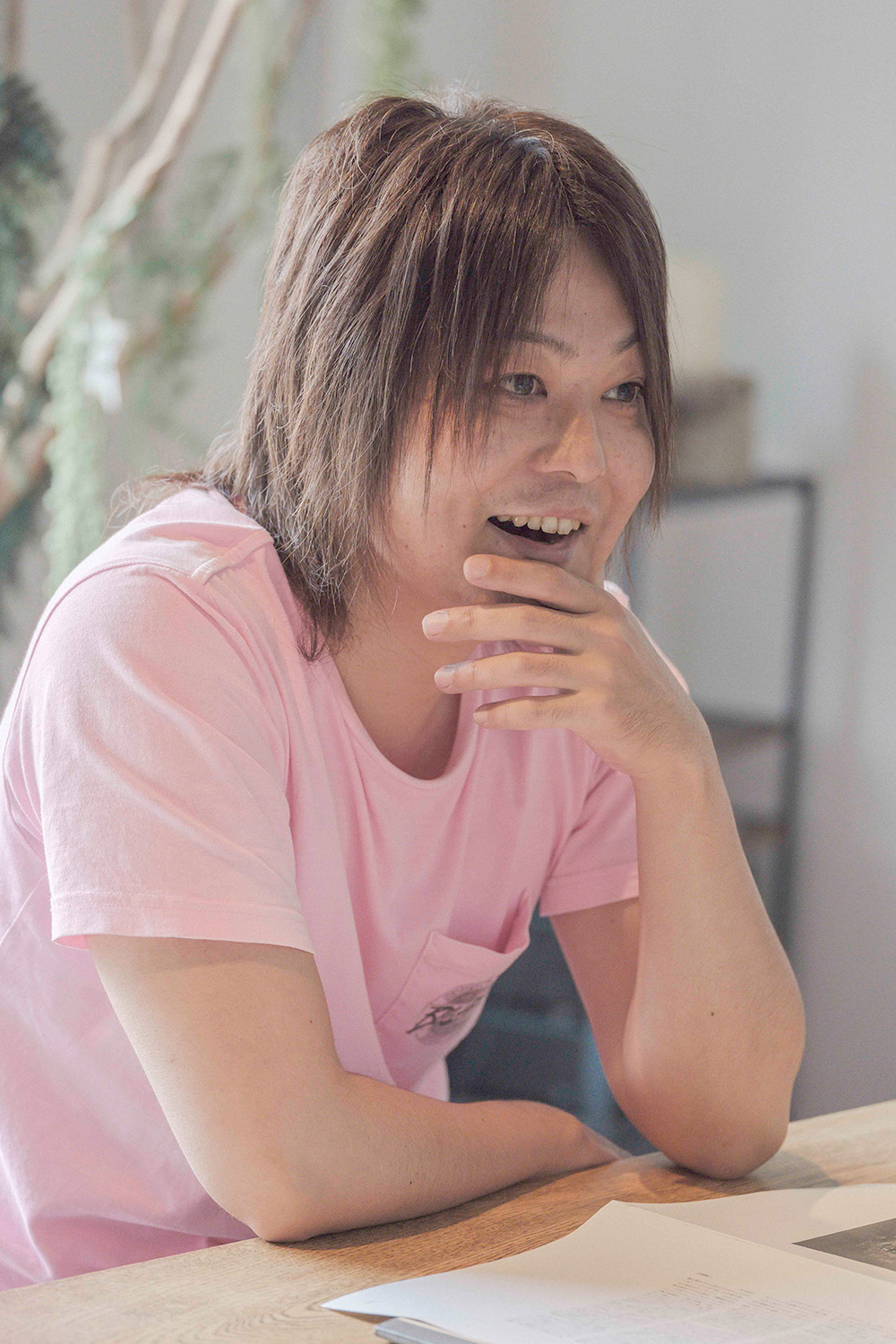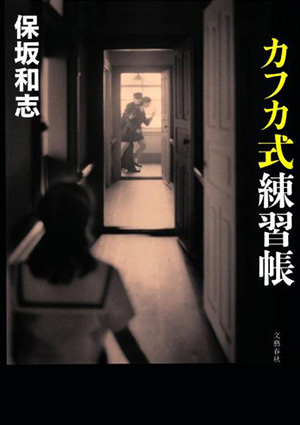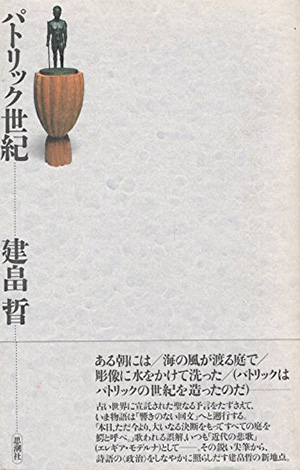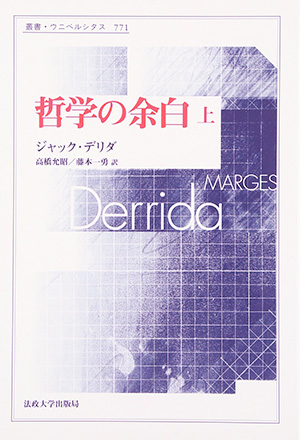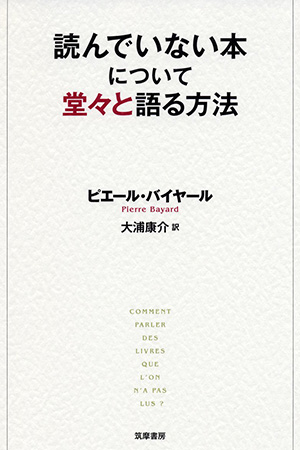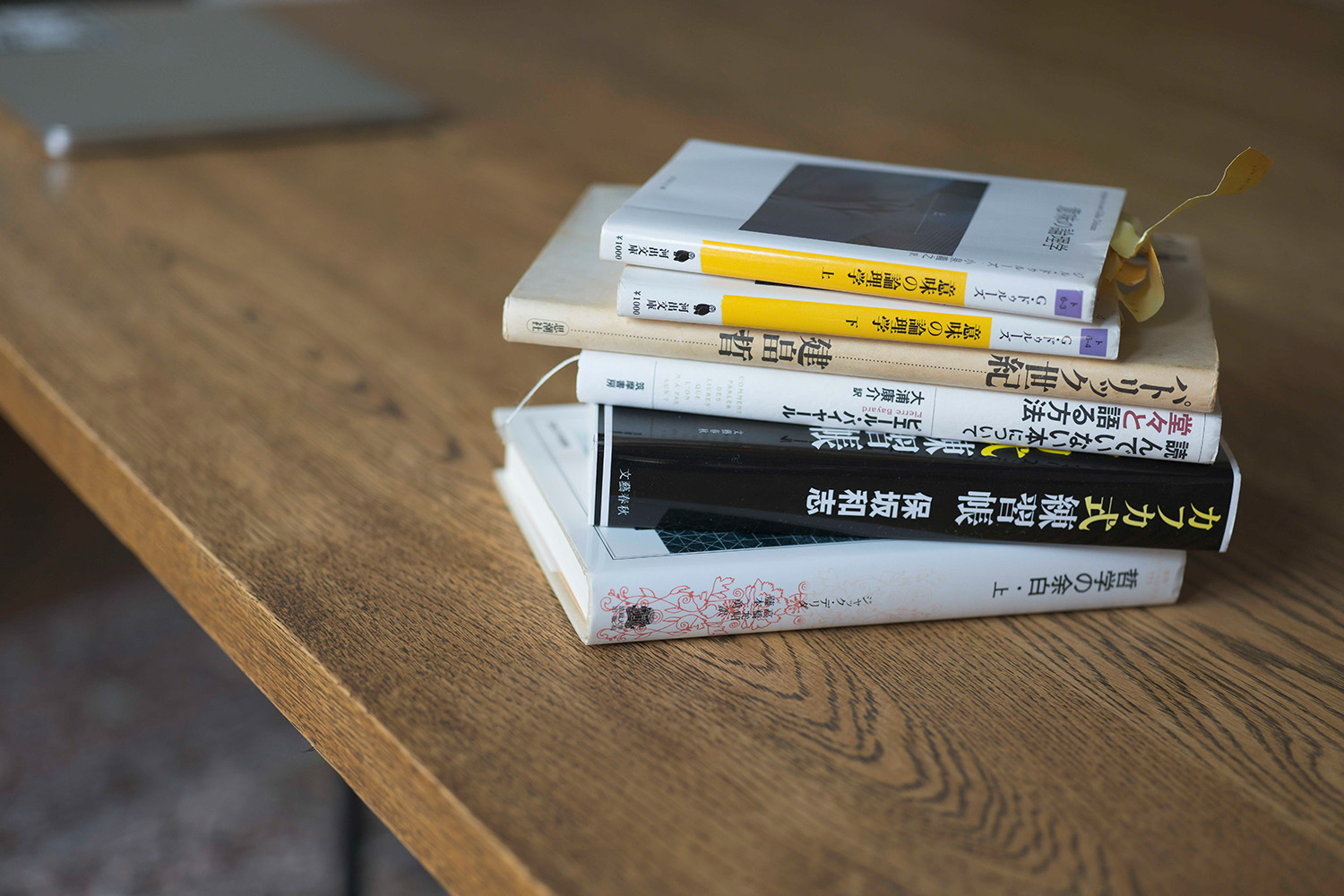書くためのツール選びに積極的になったのは、ここ数年なんです。それまではむしろ、ワープロやエディタの欠点の方が目についていました。僕は、実家がデザイン会社を経営していたこともあり、中学生の頃からDTPソフトで遊んでいたので、ついフォントや字詰めが気になってしまうんです。たとえば、ワープロの横幅ぴったりの長さで一文が終わると気持ちが悪いので、次の行にまたぐように字数を増やすなど、見た目の気持ちよさを優先して内容を変えることがあるほどでした。しかし、だんだんと文書作成・編集のためのデジタルツールが増えてきたことで、それらのツールをもっと積極的に活用できないかと考えるようになりました。
書くことに関して、僕にとって革命的だったツールはTwitterです。140字という字数制限の中で、ひとまず一つのことを書き終えなくてはいけないという仕組みが、書くことの支援になったんです。このTwitterの書きやすさについて、著書『別のしかたで——ツイッター哲学』では「書き始めた途端にもう締め切りだからである」※1と説明しています。僕は、締め切りがないと仕事ができません。他なるものに区切ってもらわないと、自分で区切れないんです。
僕は、Twitterを執筆のツールとして使っている感覚なのですが、そもそも公開のツールなので、あまり練り上げていないことを書くわけにもいかない。そこで、Twitterに近い感覚で書けるクローズドな環境はないかと考えて、WorkFlowyのようなアウトライナー(アウトライン・プロセッサ)※2にたどり着きました。
キーになるのは、真っ白な紙に長い文章を書くのではなく、ある区切られた状態で断片を書いていくということ。Twitterの場合は字数制限がありますが、アウトライナーの場合は、箇条書きというシステムが潜在的に「短く書きなさい」とプレッシャーをかけてきます。つまり、見えない可変的な字数制限があるんです。僕は、アウトライナーをそういう有限性の装置として受け止めています。
※1 「なぜツイッターの一四〇字以内がこんなに書きやすいかというと、それは、書き始めた途端にもう締め切りだからである。[2014-5-21 12:21]」p.200
※2 文書のアウトラインを組み立て、編集するためのソフトウェア。階層構造のあるテキストを管理できる。